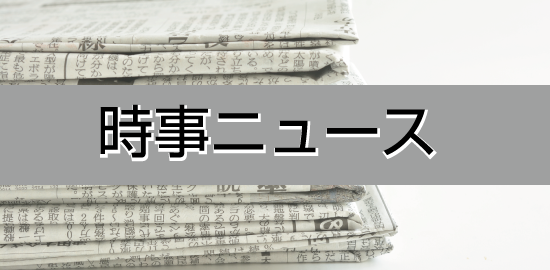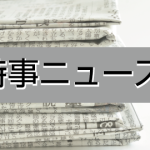年金財政検証と推計結果の概要
厚生労働省は将来の年金額の推計結果を公表し、年金保険料の納付期間を45年間に延ばす案を撤回しました。
年金財政検証は5年に一度行われる年金制度の定期健診ともいわれるもので、出生率、労働者数、経済状況について良くなる場合と悪化する場合を想定し、今後およそ100年の年金額を推計します。
その結果、出生率は多少改善し、経済成長はデフレが続いたこれまでの30年と同程度の場合、例えば2057年度で今32歳の会社員と専業主婦世帯の年金額を見ると、月額21万1000円で今の高齢者の年金額よりも18%目減りするということです。
ただし向こう100年間の年金額は法律で定めた水準よりは高く、厚労省は制度の持続性は確認されたとしています。
そして5年前の検証結果よりも見通しが改善したことから、厚労省は年金保険料を納める期間を40年から45年に延ばす案を今回の改正では導入しない考えを明らかにしました。
将来の年金支給と物価上昇への対応
今回この先100年間の年金額を試算した結果、今の若い人も将来年金は受け取れるという結果が出ました。
今の高齢者よりも年金よりも低い水準なるというのは、物価が上がる中でも年金額は増えるにしても、物価上昇率よりは低くするという調整の仕組みがあるからなんです。
これは今も行われているんですが、年金を支えるための保険料を納めている若い世代に負担をかけすぎないためなんです。
今後出生率がさらに下がる、今回ちょっと前提が出生率、甘い部分があったんですが、もっと下がるとか経済成長が低いという場合には、今回の試算より年金額が下がる可能性があります。
厚生労働省は年金額を増やすという改正を迫られているわけですけど、年金額の上昇率を抑える仕組みの変更ですとかパート労働者などを…。