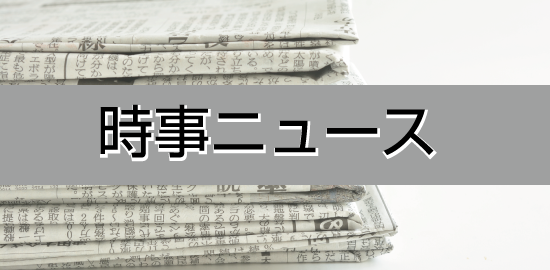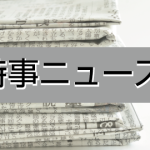米の供給量と需要の急増
農林水産大臣である江藤氏は、米の供給量について説明しました。
令和4年産米の生産量は670万トン、令和5年産米は661万トンと十分な量が確保されていたと述べています。
また、民間在庫も170万トンあったことから、需給に関する懸念は存在しないとしています。
しかし、8月の南海トラフ地震に関連した情報が流れると、消費者が急いでスーパーに駆け込み、購買量が1.5倍に急増したため、店頭から米が消えてしまったのです。
このような急な需要の増加に対し、卸業者の供給も追いつかず、米価が上がる原因となりました。
消費者への情報提供と価格の適正化
江藤氏は、消費者向けの情報提供が不足していたことも価格上昇の原因として認識し、自身の反省点として挙げています。
生産者と消費者両方にとって適正な価格が重要であり、急激な価格上昇は好ましくないとの意見が示されました。
供給量は年単位で十分確保されているため、消費行動については慎重になるべきとの見解が強調されています。