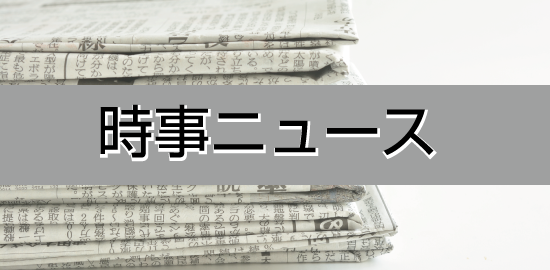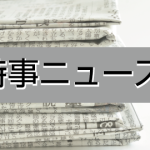地震リスクの評価と研究の進展
災害に備えるうえで重要なのが、リスクを知ることです。
都市の直下を襲った地震から30年。
私たちが暮らす場所の地下に潜むリスクを捉えようとする研究が進められています。
その1つが、京都大学防災研究所の西村卓也教授の研究。
人工衛星が捉える大地の動きから、ひずみがたまる速度を推計し、リスクの高まりを探ります。
今後30年以内にマグニチュード6以上の地震が起こる確率を算出した結果が、こちらの地図です。
赤やオレンジで示された地域で、確率が高いことを示しています。
新たな手法による内陸地震リスクの総合評価
内陸地震のリスクは、国が活断層を調査して危険度を公表してきましたが、活断層が知られていない場所でもたびたび地震が起きていて、ひとつの手法に頼ることの限界も指摘されています。
国は新たな手法も組み合わせて、総合的な内陸地震のリスクを評価したいとしています。