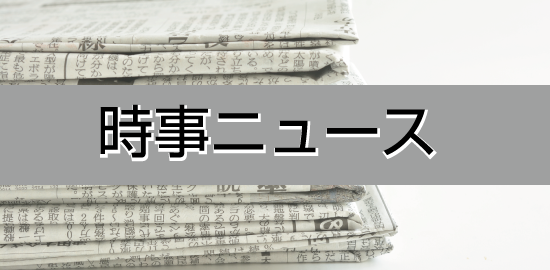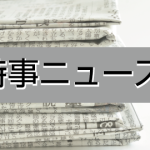バイオロギング研究の概要
が難しい海の中や空などでの生き物の生態を研究するためのものなんですけど、こうした調査の方法、バイオロギングといわれまして、計測機器を生物の体につけて、生物がどういう動きをしているのかですとか、映像のほか、位置情報、温度など、周辺の環境データを集めて調べるんです。
この知られざる生態に迫るバイオロギング研究を取材しました。
バイオロギングを使って30年近く研究をしている佐藤克文教授です。
分かっていないことが多い海での生態を、バイオロギングで解明しようとしてきました。
ウミガメは、海の中でどのように過ごしているのか。
記録装置を取り付けるのは、誤って定置網などにかかってしまったウミガメです。
記録装置はウミガメの負担にならないよう、体重の3%以下の重さで一定の時間がたつと外れる仕組みになっています。
息するかな。
どんな情報が記録されるのか。
期待して、岩手県釜石市の港から放流しました。
生態データと環境保護の重要性
生き物の生態に迫る映像自体も迫力があって貴重だと思うんですが、それだけではなくて、サケの不漁など、私たちの生活に密接に関わるデータも、最新のものとして取れるということなんですね。
距離をとりながら、生き物の負担を減らして、その暮らしに入り込むことができるという技術です。
そのデータが、厳しさを増す環境の保護につながれば、人間、それから生き物、双方にとって、有益な取り組みだというふうにいえるんでしょうね。
バイオロギングでウミガメを研究している東京大学の佐藤克文教授によりますと、計測機器の進化などにより、生態だけではなく、他の分野にも重要なデータになることが分かってきたと言います。