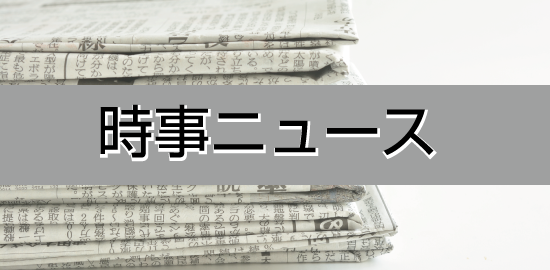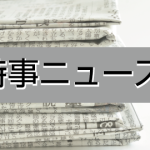イタリアの避難所環境の改善と資材整備
多くの地震に見舞われてきたイタリア。
過去には救援の遅れが問題になったこともありました。
その反省から、国を挙げて、避難所の環境や運営の方法を改善してきました。
テントやトイレなど、必要な資材を、国が中心となって全国の拠点に整備。
すぐに持ち出せる状態で保管しています。
また、ボランティアの養成と組織化も進めました。
今回参加したボランティアは、全員が訓練を受けた人たち。
ふだんの仕事や専門性を生かしたプロも多くいるんです。
日本とイタリアの避難所運営の違いと改善点
イタリアは過去の地震で救援が遅れた反省から、1980年代以降、国を挙げて議論して仕組みを作り上げてきたんです。
この市民保護局という災害対応を担う国の機関を作って、ボランティア団体との連携や調整などを進めてきたんです。
その中で、避難所についても見直しを行いました。
こちらです。
大きな災害の場合ですね、訓練を受けたボランティアがこれ、実際に被災地に入って、避難所の設置や運営を行っています。
さらに、これ、トイレやコンテナ、VTRでもありましたけれど、こうした資材はボランティア団体やこの国、市民保護局がお金を出し合って、整備をしているんです。
こうした訓練を受けたボランティアと大量の資材がこちら、災害発生から12時間以内に出動する、こういう仕組みになっているんですね。
そして、日本はこれだけ災害が頻発している、そういった国ですから、日本でもなんとかこういったことができないのかなというふうに思ってしまうんですが、この違い、日本とイタリアの違いというのは、どこから生まれているんでしょうか。
やっぱり日本でも今、災害の教訓を踏まえて、国もプッシュ型支援という仕組みを行っていますけれど、避難所の運営主体は自治体や住民が基本なんですね。
こういった状況について、専門家に聞きました。
こちらです。
避難所に詳しい、避難所・避難生活学会の榛沢和彦さん、こう指摘しています。
市町村の予算やマンパワーも限られているため、避難所の設備や環境に差が生まれている。
そして、職員も被災している中で、避難所を運営しているのが現状なので、やはり仕組みを見直すべきだと指摘していました。
もう1つ、榛沢さんが見直すべき点に挙げたことがありました、それがこちらです。
避難所は、耐えしのぐ場所ではなく、元気になる場所であるべき。
避難所の環境をよくすることは、復興への早道にもつながるということなんですね。
私もイタリアでの取材中、印象に残ったことがありました。
なぜこういうふうにできるんですかと聞きますと、ボランティアの人たちが、ベネッセレということばを口にしていました。
これ、どういう意味かといいますと、精神的な健康や快適さを意味してるんですね。
まさにこれが志なんですね。
日本の避難所はもしかしたら、被災した住民や地元の職員の我慢や忍耐に寄りかかっていないでしょうか。
心と健康を守るために、質の高い避難所を社会全体で作っていく必要があると思います。