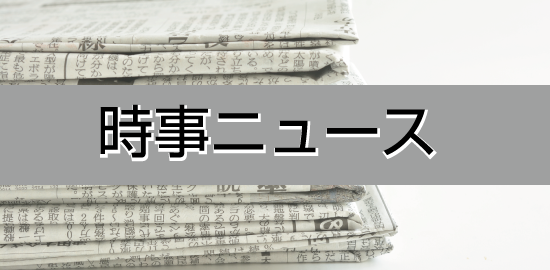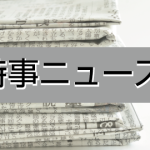萩野さんと藻の出会い
萩野さんが藻に出会ったのは高知大学の学生だったとき。
その後、子育てと両立するため、大学ではなく主に自宅で研究を続けてきました。
この部屋で研究していたのが、あのサイエンスの表紙を飾った藻です。
その名も、ビゲロイ。
大きさは100分の1ミリほど。
これまでは詳しい特徴は分かっていなかったんですけども、萩野さんは30年以上、その生態を研究しています。
今回の発見、鍵となったのは、培養です。
詳しい生態を知るためには、多くの個体を確保して調べる必要があります。
ただ、生息域も分からなかったため、培養のおおもととなる個体を探すことから始めました。
ビゲロイの培養成功とその可能性
この培養成功は、ビゲロイが窒素を取り込む能力を持つという発見に大きな役割を果たしました。
安易におっしゃっていますが、長い年月、苦しみもあったと思います。
研究が進んで農業分野にこれ、応用できれば、ビゲロイと同様に窒素を直接取り込める野菜が作れる可能性があるのではと期待されています。
高知から世界へ、そして小さな藻が秘める大きな可能性に期待が寄せられています。